世界の多くは右側通行、でも日本は左側通行?
海外旅行やドライブ好きの方なら一度は疑問に思ったことがあるはず。「なぜ日本は左側通行なのか?」
アメリカやドイツ、フランスなど多くの国では右側通行が採用されていますが、日本やイギリス、オーストラリアなど一部の国では左側通行が主流です。
実は、この「通行方向」には深い歴史と文化、時には戦争や国家の威信が関係しているのです。
今回は、日本がなぜ左側通行を採用しているのか、そして世界の通行方向の歴史について、わかりやすく解説します。
そもそも「通行方向」はいつ決まった?
道路の通行方向は、古代ローマ時代にはすでに意識されていたと言われています。
ローマ帝国では左側通行が基本とされていたという説があります。理由は、右利きの兵士が右手に剣を持ち、すれ違う相手をすぐに攻撃できるようにするため。また、馬車の御者が鞭を振るいやすい位置に立てるという利便性もありました。
このように、「通行方向」は安全性と利便性の観点から自然発生的に形成されていったのです。
ところが中世以降、ヨーロッパ大陸では徐々に右側通行へとシフトしていきます。その転換点となったのが、あのナポレオンです。
ナポレオンの影響で「右側通行」がヨーロッパで広がった
フランス革命以降、ナポレオン・ボナパルトはフランス軍に右側通行を徹底させました。これには、「貴族階級が左側通行をしていた」という旧体制の象徴を打ち壊す意図があったとも言われます。
その後、ナポレオンの征服活動により、フランスの影響を受けた国々でも右側通行が広まりました。
これがヨーロッパ大陸における「右側通行」の大きな流れを生むきっかけになったのです。
例えばイタリア、スペイン、ポルトガル、ポーランドなどもこの流れに追随しました。一方で、ナポレオンの支配を受けなかったイギリスやスカンジナビア諸国では左側通行の慣習が残り続けました。
日本が左側通行になった理由とは?
日本で左側通行が根付いた背景には、いくつかの要因があります。
1. 武士の刀の携帯方法
江戸時代、武士たちは左腰に刀を差していました。すれ違う時に鞘がぶつからないよう、自然と左側通行が浸透したとされています。道幅の狭い江戸の町では、無用なトラブルを避けるために左側通行が望ましかったのです。
2. 明治時代の鉄道整備
明治時代、日本初の鉄道(新橋〜横浜間)を整備したのはイギリスの技術者たちでした。イギリス式に倣って、鉄道は左側通行で設計されたのです。
鉄道の整備は近代化の象徴であり、交通インフラのモデルケースとなったため、道路交通も鉄道に倣って左側通行が定着しました。
3. 交通法令による明文化
1900年(明治33年)に「道路取締令」が制定され、明文化された形で左側通行が正式にルール化されました。さらに戦後の1950年、「道路交通取締法」によってその原則が引き継がれ、現在の道路交通法へとつながっています。
このように、日本では歴史的な慣習と制度的整備が相まって、左側通行がしっかりと根付いたのです。
世界の「通行方向マップ」
現在、世界のおよそ65%の国が右側通行を採用しており、35%が左側通行です。
左側通行の国には以下のような国があります:
- 日本
- イギリス
- オーストラリア
- インド
- タイ
- 南アフリカ共和国
- アイルランド
- ニュージーランド
- シンガポール
興味深いことに、これらの国々の多くはイギリスの旧植民地であり、イギリスの道路制度がそのまま移植されたケースが多く見られます。
また、国境をまたいで通行方向が変わる地域もあり、タイとラオスの国境では、橋の中央で車線を切り替える構造が採用されています。
まとめ:日本の左側通行は歴史と文化の結晶
日本が左側通行なのは、単なる偶然や利便性の問題ではありません。
それは武士の文化、イギリスの影響を受けた鉄道の発展、そして明治政府の近代化政策という、歴史と制度の積み重ねによるものなのです。
世界の国々で異なる通行方向を知ることで、交通の背景にある文化や歴史に気づかされることがあります。
次回、海外旅行や国際ニュースで「通行方向」が話題になったときには、ぜひこの記事を思い出してみてくださいね。
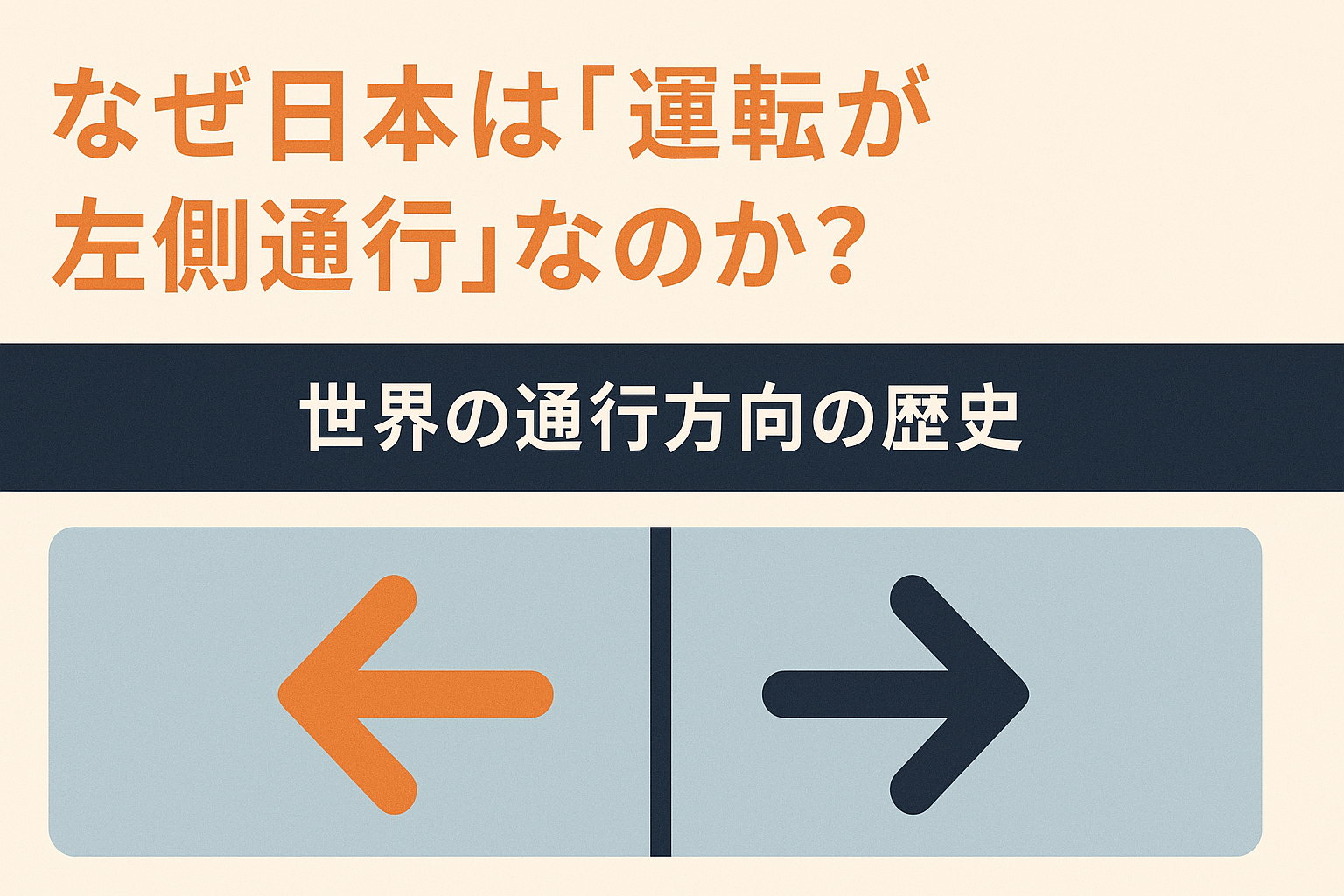

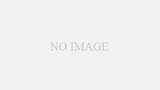
コメント