みなさんが学校で使っている地図や、スマホで見る地図を思い出してみてください。ほとんどの地図では「北」が一番上にありますよね。
でも、ちょっと不思議に思いませんか?
地球って丸いのに、どうして「北」が上って決まっているんだろう?って。
実は昔の地図は、今とちがって「南が上」に描かれていたこともあったんです。今回は、そんな「地図の上と下」について、歴史や文化の話も交えながら、わかりやすく紹介していきます!
■ 昔の地図では「南が上」だった!?
今では当たり前のように北が上になっている地図。でも、昔の人たちはちがう考え方をしていました。
たとえば、昔のイスラム世界の地図は、南を上にして描かれていたんです。イスラム教の聖地メッカが南の方角にあったので、それが中心になるように地図が作られていました。
また、中国の昔の地図でも、南を上に描くことがよくありました。中国では、皇帝(こうてい)などの偉い人が南を向いて座るという伝統があり、それを大切にしていたからです。
さらに、古代エジプトの壁画などでは、太陽が昇る「東」を上にすることもありました。
このように、「上が北」というのは昔からのルールではなく、文化や考え方によって変わっていたんですね。
■ 北が上になったのはなぜ?
では、どうして今では地図の「上」が北になっているのでしょうか?
その理由はいくつかありますが、特に大きなきっかけになったのは、**ヨーロッパの大航海時代(だいこうかいじだい)**です。
この時代、ヨーロッパの人たちは船で世界中を旅するようになり、地図や道具がとても大事になりました。
● コンパスが北を指すから
まず一つ目の理由は、「コンパス(方位磁石)」です。これは、針がいつも北を指す道具です。
船乗りたちは、コンパスを使って進む方向を決めていました。だから、地図もコンパスと同じように北を上にしたほうがわかりやすいんです。
これによって、だんだんと「北が上」の地図が広まっていきました。
● メルカトル図法の登場
二つ目の理由は、**1569年に作られた「メルカトル図法」**という地図の描き方です。
これは、オランダのメルカトルという人が発明した方法で、船で旅をするときにとても便利な地図です。地図の上を北にしておくことで、まっすぐ進む方向がわかりやすくなり、航海がスムーズにできました。
この地図の登場も、「北が上」が当たり前になるきっかけになったんですね。
● ヨーロッパ中心の考え方
そして三つ目の理由は、ヨーロッパの国々が地図を作る側だったからです。
ヨーロッパは北半球にあるので、北を上にした地図では自分たちの国が地図の上のほうに来ます。これによって、自分たちの国が「偉い」ように見える、という考え方もあったのではないかと言われています。
つまり、「北が上」になったのは、技術の進歩や便利さ、そして国々の立場や考え方が関係していたんですね。
■ 地球に「上」や「下」はない!
ここで大事なことを一つ。
地球には、本当は「上」や「下」なんてありません。北と南はただの方角です。
地図の「上」を北にしているのは、人間が決めたルールにすぎないんです。だから、世界の見方を変えれば、「南が上」でもぜんぜんおかしくありません。
実際に、
- オーストラリアでは、南が上になっている地図が売られていることもあります。
- 教育の現場では、「上下を逆にした地図」を使って、世界の見え方を考え直す授業が行われることもあります。
地図を見るときは、「これはどこからの目線で作られた地図なのかな?」と考えてみると、いつもとちがう世界が見えてくるかもしれません。
■ まとめ:地図には歴史と文化がつまっている
「北が上」という地図の形には、長い歴史とさまざまな考え方が関わっていたことがわかりました。
- 昔は南や東が上の地図もあった
- コンパスや航海に便利だから北が上になった
- ヨーロッパの国々が広めた
- 本当は地球に上も下もない
私たちが当たり前だと思っていることも、少し目線を変えるだけで、まったくちがって見えることがあります。
地図は、ただの「道しるべ」ではなく、その時代の人たちの考え方や文化がつまった、世界を映す鏡のようなものなんですね。
今度、地図を見たときは、ぜひ「なぜこの形なのか?」を考えてみてください。
世界がもっと面白く見えてくるはずですよ!

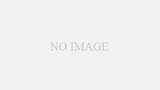

コメント